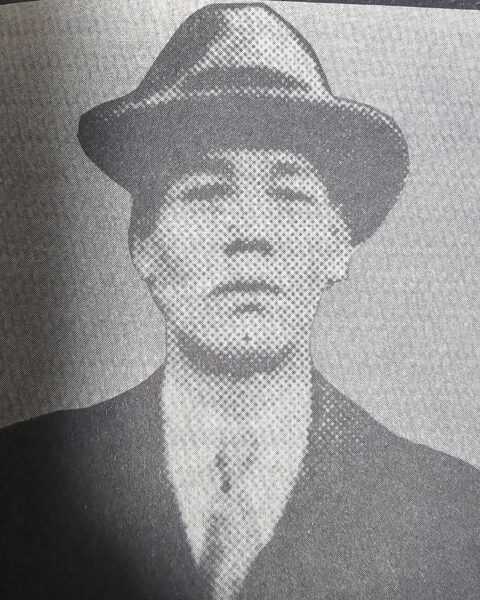
山口組、山口春吉組長。
山口春吉初代は日露戦争の兵役を終えた後の明治39年頃、淡路島での漁師生活に見切りをつけ、妻と幼い登(後の二代目)を連れて神戸に移った。
荷役請負業、倉橋組の労働者として働き始め、その屈強な体と統率力で、たちまち労働者を束ねる役回りとなり、大正2年頃、神戸港で傑出した勢力を持っていた大島組の大島秀吉の舎弟盃をもらった。
神戸ヤクザのルーツは、九州ヤクザに連なる。
筑豊の大親分で、後の国会議員も務めるようになり、近代ヤクザの祖と言われる吉田磯吉の配下にいた富永亀吉が神戸にやって来たのが明治中期だった。
富永は炭鉱で納屋頭を務めた経験を生かして、港湾荷役労働者を束ねて富永組を起こし、神戸ヤクザの祖と言われる。
その富永が神戸に呼び寄せた客分が大島で、兵庫運河の近くに大島組の看板を掲げて勢力を拡大し、運河の親分と呼ばれた。
大島は、大正12年に富永が敵対勢力に殺害されるなどしたことから、神戸最大の親分として君臨するようになる。
春吉初代の舎弟となったのはその10年前のことで、これも先見の明と言えよう。
大島組の傘下として力をつけた春吉初代は、大正4年、労働者50人を抱えて山口組を起こした。
山口組は博徒ではなく、資本主義を背景に生業を持つ近代ヤクザとしてスタートしたのである。
春吉初代は沖仲仕ばかりでなく、魚市場の荷役請負などにも事業を拡大。
さらに、神戸市議会議員で劇場経営も手掛けていた福森庄太郎の知遇を得て、当時人気絶頂だった浪曲の興行を手掛けるようになり、また相撲興行にも進出していった。
当時はまだ興行に関わるヤクザは少数だった。
こうして山口組の勢力は、本家筋の大島組に匹敵するほどまでに拡大していった。
春吉初代は大正14年に40歳になるのを機に引退し、跡目を実子の登二代目に譲った。
登二代目はまだ23歳の若さだったが、10代前半で愚連隊の幹部を叩きのめすなど、ヤクザの親分としての資質は明らかだったから、跡目を譲ったのであろう。
さらに自身、大島の舎弟であることから気を遣わざるを得ないが、こうしたしがらみのない登二代目なら、思う存分にその才覚を発揮でき、山口組がさらに発展するとの思惑もあったのではないだろうか。
引退した春吉初代は事業に専念し、のちに山口組合出資会社を設立し、その社長に就任している。
同社は昭和7年に山口組がその権利を独占した神戸中央卸売市場の荷役運搬業事業に当たった。
ヤクザ組織としての山口組の運営は、二代目、登二代目に任せ、自らが事業の面でバックアップしたわけである。
ここにも春吉初代の近代ヤクザとしての才覚が見て取れる。
春吉初代は昭和13年1月17日、57歳で波乱の生涯を閉じている。
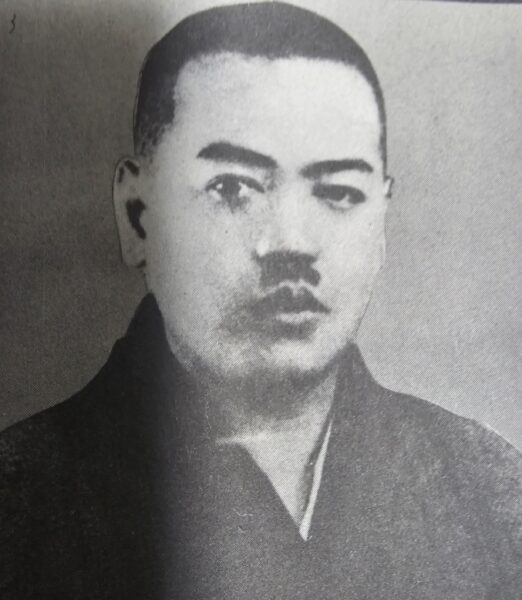
二代目山口組 山口登組長。
大正14年に23歳の若さで、実父・山口春吉初代から二代目山口組を継承した登組長は、小柄だが腕っぷしは強く、根っからの親分肌で激しい気性の持ち主だった。
登二代目は襲名してまもなく、港の顔役として全国に知られた鶴井組の鶴井寿太郎や、酒井組の酒井新太郎、藤原組の藤原光次郎と兄弟分となった。
そして対象15年、その3人の頭文字を取り、全国の港湾人気業者を一本化すべく作られた鶴酒藤兄弟会が結成されると、その神戸責任者となった。
また、昭和5年に神戸中央卸売市場の開設が決まると、登2代目はその予定地の目と鼻の先に本拠を移した。
市場で荷役運搬の権利を獲得しようとしての行動だが、ここは本家筋の大嶋組の縄張りあり、そこに公然と手をつっこんだのである。
激怒した大嶋は、登二代目を破門処分としたが、だがそれに動じないどころか、激しい抗争の末に昭和7年に市場が開場するとその利権を独占した。
これにより山口組は、初代の兄貴分であった大島組のくびきから解放され、独立組織となり、登二代目は切戸の親分として確固たる地盤を築いたのである。
さらに、初代が先鞭をつけていた浪曲興行にも本格的に進出していった。
山口組興行部を起こし、興行界の重鎮であった浪花家金蔵や永田貞雄と親交を結び、神戸の八千代座で東西浪曲一流大会を開催して大成功を収め、全国的な浪曲興行に影響力を持つようになった。
また、吉本興業の吉本せいと信頼関係を築き、地元代議士の応援弁士として活躍し、政治家とのパイプも持った。
こうした力もあって、浪曲ばかりではなく、歌謡曲や大相撲の興行も手中におさめていった。
昭和15年、吉本興業がその出資権を握っていた人気浪曲師・広沢虎造が、山口県に本拠を置く名門組織・籠寅組の要請で、映画出演を勝手に承諾してトラブルとなった。
吉本興業の依頼で登二代目が籠寅組と掛け合い、さらに虎造のマネージャー役でもあった浪花家金蔵と話をすべく、東京浅草の事務所にも出向いた。
すると、そこに籠寅組の刺客が日本刀などを手にして急襲。丸腰の二代目は瀕死の重傷を負い、同行していた客分の中島武雄は死亡した。
山口組組員が報復のため続々と上京したが、関東国粋会の客分で仲裁もあって手打ちとなった。
その手打ち会には、関東のそうそうたる親分衆や、陸軍大将も立ち会った。
登二代目の傷は回復したが、2年後の昭和17年、旅先から帰途に脳溢血で倒れ、神戸の病院に運ばれ、同年10月4日、41歳の若さでこの世を去った。
戦時中という時代もあり、山口組はしばらくの間跡目を決めず、幹部らが山口組兄弟会を作って組の運営にあたった。
三代目の誕生を見るのは、終戦を迎えてからとなった。